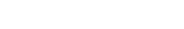織物の良さを
一貫生産の工場から発信する
――小嶋織物は、1966年(昭和41)に織物壁紙の生産販売をスタートされています。織物壁紙の製造は、どのような経緯で始められたのでしょうか?
小嶋社長 当社は2025年(令和7)で創業93年目、法人化して64年目です。隣の奈良県には古くから蚊帳や蚊帳ふきんの製造が産業としてあり、その文化が木津川市にも入ってきて、やがて蚊帳の技術から、ふすま紙が誕生しました。
1970年の大阪万博の際、周辺にたくさんの集合住宅が誕生しました。そこで自然素材の温かさと独特の質感を持つ織物壁紙が大変な人気となります。その社会の流れを受け、ふすま紙を製造していた当社でも、緯糸を太くしたらどうなるかといった技術を試し、織物壁紙の製造をスタートさせました。
この頃は全国的に新たな産業として壁紙が注目されており、当社が蚊帳の技術からふすま紙、そして織物壁紙へと事業を拡大していったように、愛知県の一宮市など、繊維産業が発展していた地域でも、次々と織物壁紙の製造が始まっています。
――織物壁紙は糸を撚(よ)り、色を染め、織り上げるという、大変手が掛けられた製品です。小嶋織物の特徴や強み、守り続けるこだわりはどのようなところでしょうか。
当社の一番の強みは、提案から製造まですべて自社で可能なことです。自社工場を持っていることにより、試作品の依頼にも1〜2カ月でお応えできます。また、糸も持っていますから、ひとつの依頼に対して、緯糸を各種使い、表情が異なる複数の提案も可能です。

小嶋織物の自社工場
――織物壁紙を使用した空間づくりの魅力や利点を教えてください。
「織物壁紙を使用している室内は空気感が違う」とよく言われます。その要因は織物が持つ漆喰の壁のような調湿性のほか、通気性や吸音性といった特性によるものです。「織物壁紙の部屋はよく眠れる」という感想をいただいたこともあります。
織物壁紙は綿や麻などの天然素材を使用している物もあり、サステナブルな特徴があります。また、触ったときのふわふわ感、もわもわ感、ボリューム感、温かみがあるといった特徴もあります。当社はメーカーとして、この良さを製品としてお届けしていくことにこだわり続けています。
和風から洋風まで
イメージは無限大
緯糸次第で豊かな表現が多彩に
――小嶋織物が手がける壁紙の中でも、特に人気のあるシリーズについて教えてください。
時代を超えて支持されているのは、やはり白やアイボリーといった自然な色合いのシリーズです。また近年では、「オーガニックコットン壁紙」が環境や健康に配慮したライフスタイルを求める方々から高い評価をいただいています。緯糸(よこ糸)にオーガニックコットンを使用した優しい風合いが特徴で、子ども部屋の壁紙としてご家庭に取り入れていただくことも多いんですよ。
――小嶋社長ご自身がおすすめされる壁紙はありますか?
少し個性的ですが、WWT30401(ノマドワークス)はダイナミックながら素朴な風合いが他には無いデザインだと思いますね。この製品は台紙の上に薄い生地を手作業で貼り付けるという特殊な製法で仕上げています。
また、通好みの一品としては、WWT30417~30420(古今)シリーズもぜひ注目いただきたい製品です。普遍的な和小紋柄に渋い色味を施した落ち着きのある壁紙で、日本の伝統美を大切にする方々に響く一品です。同じ古今シリーズでも、色調の違いによって空間の印象が大きく変わる点も魅力のひとつです。
また、変わり種だと「デニム壁紙」というラインナップも展開しています。これは一般家庭というよりも、アパレルショップなどの商業空間で使用されることが多く、独創的で記憶に残る店舗デザインを実現できる素材ですね。(SWT30113~30114)
――SWT30105~30107やSWT30108~30111シリーズは、織物壁紙の中でも特にモダンな印象を感じますが、開発にあたって苦労された点はありますか?
これらのシリーズは、モダンな雰囲気を追求しながらも建築基準法で定められた不燃性能をクリアするという二つの課題を両立させるのに苦心しました。使用している紙糸は本来軽量なため、不燃素材の認証取得に必要な基準を満たしつつ、織物壁紙としての豊かな質感とボリューム感を損なわないよう工夫しました。最終的には技術的な挑戦を乗り越え、現代建築にマッチするモダンな表情と高い安全性を兼ね備えた製品に仕上げることができました。
――日本らしい風合いを持ちながらも、モダンで現代様式の住宅やホテルなどにもマッチする製品を数多くつくられていますが、デザインを検討する際に意識していることは?
織り方はもちろん大事です。それに加えて、色にもこだわっています。たとえば4色の糸を交わらせることで個性的な表現ができる糸になりますし、同系色でも、ブラウンを濃淡で交わらせると色が引き立ちます。織り方の中でどういうイメージを見せるかというのは、色の影響が強いと考えています。畳のグリーンだったら和になるけれども、アメリカで売れているグリーンはもっと鮮やかなグリーンですから洋になってしまうというように。
ほかにも、博物館では展示物の背後の織物壁紙が照明の光をある程度吸収して作品を際立たせ、高級ホテルの廊下では織物壁紙を貼ってダウンライトを当てると、それだけで雰囲気が一変します。このように、使われる場所の光についても、デザイン面では意識する必要があるわけです。
当社は蚊帳製造の技術を壁紙で展開し、いわば伝統の技術を現代の空間に合わせていく一端を担っています。その面でも、和洋問わず空間の質を上げるデザインを心がけていかねばなりません。
織物壁紙で四季を楽しむ暮らし
商業施設から家庭まで
幅広く活躍

――作り手の立場から、織物壁紙はどのようなシーンで活躍するとお考えでしょうか?
昭和の一般家庭では季節ごとに襖を変え、部屋ごとに壁紙が異なっていることもありました。当時は家が資産であり、家での時間を誰もが楽しんでいましたから、ふすまの絵柄で季節を楽しむことも大切な暮らしの要素でした。
近年の住宅からはふすまが減っていますが、壁紙はあります。だから単なる資材ではなく、織物壁紙で日本の四季を感じてもらえるようにしたいですね。
そう考えると美術館やホテル、インテリジェンスビルといった商業的な施設だけでなく、先述した織物壁紙が持つ性能を生かせる一般家庭の子ども部屋や寝室でも、活躍できると考えています。
技術力の向上が今後の課題
日本で拡げ、伝えることが
未来を創る
――御社の技術を次代に引き継いでいくこと、そして御社の織物壁紙がさまざまな場所で取り入れられ続けていくことへの思い、今後のチャレンジについても教えてください。
技術力を上げていくことが、事業計画と技術継承の両面で重要だと考えています。しかし、質を上げるには量が必要です。そういう意味で、織物壁紙の存在を伝え、販売につなげていく今後の事業展開の構築が急務だと考えています。
これは当社だけでなく、繊維業界全体としても考えていかねばなりません。そのために織物紙壁紙工業会で、伝え、売っていくための広報活動を進めています。会員全体でオープンファクトリーの開催や展示会出展をし、PRをしているところです。
以前展示会に出展した際、女子学生が「こんな壁紙見たことない」と、壁紙を何度も触っていました。若い世代は、壁紙にもさまざまな種類がるということ自体を知らないんですよね。そこで「見たことない」をどうPRしていくかも検討しています。織物壁紙の質感は見本帳だけでは伝わらないため、体感していただけるショールーム的な空間を当社独自で造っていくべきではないかと検討しています。
海外では一定の需要はありますが、やはり日本人に知っていただき、使っていただくことが嬉しいのです。だから店舗や施設だけでなく、織物壁紙のある暮らしを一般家庭に広めたい。
素材系壁紙が見直されはじめていますが、まだまだ多くがビニールの製品です。そこで織物の良さをもっと伝え、素材系壁紙といえば織物壁紙との認識を増やしていく。技術力の向上や技の継承と事業展開はセットです。だからこそ、伝えるためと販売を増やしていくための活動を両輪で回していくのが、これからの当社のチャレンジです。