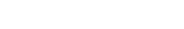現代建築の壁を越える和紙クロス
――井上さんは表具師として、掛軸や額、屏風、衝立、巻物等、数多くの表装の新調・修復を手掛けられている傍ら、近年では、現代アートと表具の伝統材料を融合させ、現代の建築様式に合う表具の在り方を模索されています。まずは改めて、井上さんの現在の活動内容について教えていただけますか。
井上雅博さん(以下、略) 表具師の仕事は、工房で行う掛軸や屏風などの作品制作や修理のほか、現場作業があります。
現場作業というのは、具体的にいうと、全国の社寺や数寄屋建築での襖や障子、壁面和紙貼りなどの内装施工です。表具店さんのなかには、襖専門や屏風専門でやられているところもありますが、私が手掛ける範囲は幅広いですね。
ここ最近は、京都でも新しいホテルがどんどん建ち並ぶようになっていますが、“京都らしさ”といいますか、日本の良さを出したいというご要望から、和紙貼りのご依頼をいただくことも増えています。
ただ、例えば昔ながらの和紙貼りは、そもそも使う素材(=和紙)からして、現代建築においては法規制の基準に満たないために難しい。そうした際に、シンコールさんをはじめ、クロスメーカーがつくられている不燃和紙などのクロスを使わせていただいています。私たち表具師にとっても、wall proのようなクロスはなくてはならないものなんです。
――法規制の観点から使用が難しくはなっているものの、やはり和紙をはじめ、日本らしい素材を空間に用いたいという希望は多いと思います。井上さんは、そうした日本の伝統技術をホテルなどの現代の建築様式に融合させていくことについて、どのようなお考えをお持ちでしょうか。
そもそも井上光雅堂は、祖父が京都国立博物館内の国宝修理所で表具師をしていたことがルーツにあります。独立して今の店を構えることになり、そこから一般的な建築物の表具も行うようになりました。
私の代になってからは、先述したような建築に関連する基準や、人々のくらしも大きく変わってきました。同時に、アーティストや作家さんから生まれる作品も、飾られる建築、ホテルや飲食店、住居の様式に合わせてどんどん変化しています。
表具師の本来の仕事は、書や絵画などの作品を、さらに美しく引き立てるための表装を施すこと。そして、その作品が置かれた空間の居心地良さをつくり出すことが、大事な役割です。数寄屋建築の内装や襖の柄選びにしても、どんな和紙を障子に貼ると光の入り具合が良くなり、そこに飾れた掛け軸が美しく見えるのか、人が過ごして気持ちのいい空間になっていくのかを考えていきます。私からどんどん新しいことを仕掛けているわけではなく、建築の内装デザインや作品の変化に合わせて材料を選び、私自身も変化し続けてきたんです。

井上さんは、「表具の伝統材料×ART」をテーマに、現代の建築様式に合う表装を模索しながら、新たな和のしつらいを追求しています。
――様式の変化によって、使う道具や素材なども変わってきているのでしょうか?
井上光雅堂には「京表具」という名称が付いています。「京」というのは京都の「京」です。これは、京扇子や西陣織など、のべ74品目の京都の伝統工芸をつくるにあたり、昔からの技術を守っていく、京都から指定された表具師であることを指しています。具体的には、市内の指定業者が扱う、京都付近で採れた材料を使わなくてはいけなかったり、昔からの使い方を変えてはいけなかったりと、さまざまな指定がある。伝統を守るために、変化してはいけない部分も多くあるのです。
一方で、作家さんによっては日本画の画材を使わずに作品をつくる方もいますし、建築においても、不燃材料でなくては内装を手掛けられないことも多くなっている。そうした際には、今までのやり方を取っ払わなければ先に進めません。状況に応じて「京表具」の表具師ではなく、ひとりの表具師として、使い分けを大事にしながら作品や空間に向き合っています。
wall proは「空間を心地良いものにする」を追求するための“選択肢”
――素材壁紙見本帳・wall proは、日本の伝統的な技術を建築空間のなかに取り込むことを目的とした商材です。井上さんは状況に応じて京表具師と表具師の役割を使い分けていらっしゃるように、wall proもまた、状況に応じた選択肢のひとつとして位置づけられるものなのではないかと感じました。井上さんは役割が変わっても、表具師として変わらず大切にされている技術や手法はありますか??
例えば昔から受け継がれてきた壁面和紙貼りには、空気中の水分を吸ってくれたり、日の光を柔らかく受けてくれたりと、快適な空間をつくるためにこの素材を用いる“意味”があります。
それだけでなく、和紙貼りの技術は、壁紙の持ちを良くするという点でも理にかなっていました。和紙貼りでは、あえて継ぎ目を見せる「三分継ぎ」という貼り方をするのですが、これは、伸縮する和紙が部屋の乾燥によって縮んできてしまったときに継ぎ目に隙間ができないようにするための工夫です。
もちろん、機能性だけでなく、見た目の美しさにもこだわりが込められています。継ぎ目は「右上前」にしないといけなかったり、下地の凹凸の影響が出ないように、貼る前の壁面を限りなく真っ平にする壁面処理には膨大な時間がかかったりと、そのために手間のかかる工程がたくさんあります。その手間暇のすべてが、空間を心地よいものにしてくために必要な仕事なのです。

井上さんが自ら和紙貼りをしたご自宅の壁面。三分継ぎの凹凸もデザインとして生かされていました。
和紙クロスを用いる際にも、もちろん、素材は扱いやすくなりますが、継ぎ目の考え方などは変わりません。私はあえて、継ぎ目をデザインにして遊びの要素として取り入れるといったアレンジもしつつ、現代の建築様式のなかでも守るべきポイントは大切にしています。
こうした背景をお客様にお話しすると、手間暇がかかるからこその良さを皆さん喜んでくださいますね。
――日本のサステナブルな暮らしのあり方が再評価されている今、手間がかかっても、伝統的な技術にあえて立ち返っていくという考えは、ますます支持されているように感じます。
そうですね。仕上がったときの出来栄えを見ると、お客様は「やっぱり和紙を使うといいね」とおっしゃいます。伝統を守ろうとか、技術が大事と言われてもピンと来ないけれど、実際の仕上がりが良ければ納得してもらえると思います。
――「空間の居心地の良さ」は、日本の歴史や伝統を知らずとも、感じ取ってもらえるものだと思います。海外の方からの反響もあるのでしょうか。
昨今では、技術を応用して活用の場面もさまざまに広げていて、国内外の方々の目に触れる機会が増えているのは事実だと思います。例えばフランス・アルルの国際写真展では、作家さんの写真を飾る壁を和紙でつくるために現地まで足を運びました。中世ヨーロッパの建物のなかで、日本の作品をどうカッコよく魅せられるか。背景を和紙で飾ることで、堅牢な建物のなかの柔らかさを浮かび上がらせようと考えたのです。
実はその際も、使用したのは和紙クロスです。クロスだからこそ、海外への輸送や設置も負担が減って、イメージ通りの表現ができたと感じています。おかげでアルルの写真展も大成功でした。
応用の可能性を広げるwall proの使い方ポイント
――wall proも、「壁紙」として部屋の壁に貼るだけでなく、その空間や芸術作品の一部として、さまざまな応用の可能性があるのかもしれませんね。最後に、wall proの使い方のポイントについて、おうかがいできますか。
そもそも壁面の和紙貼りは作業が大変なために、数寄屋建築においても茶室に限られるなど、ポイントを絞って使われてきました。現代の生活様式のなかでも、伝統技術や、それを用いたwall proのような高級クロスはここぞという大事なところに使って行く、その選択肢のひとつになっていければいいのかなと思うんです。どんな空間にしたいか、どう過ごしたいかという家主の思いがあり、それに合わせてどんな材料を組み合わせていくかを提案することが、表具師の仕事でもあります。
背景にどんな素材を当てるかで、空間の印象は一変します。作品の目の前に立ったとき、その空間に入ったときに感じる「気持ち良さ」「心地良さ」をいかにして引き立てるのか。今はクロスによって、一般の住宅建築では用いることが難しいような技術が必要な壁面も再現できることがありますから、まずは取り入れて、その違いを実感していただきながら、伝統と現代の様式を融合していってもらえたらいいんじゃないでしょうか。


SW30055、SW30060
SW30055
商品ページへSW30060
商品ページへ様々な表情の和紙クロス
wall proでは、越前和紙や因州和紙などの伝統的な和紙クロスを取り扱っています。今回は掲載商品から3点をピックアップしてご紹介します。
SW30017 越前和紙 品の良いさくら色が上質な和空間に合う、エコマーク取得商品です。


SW30017
SW30065 因州楮大雲竜和紙 大きな雲竜を漉き込んだ、迫力ある和紙壁紙です。ほのかな光沢で洗練された高級感。


SW30065
WWT30353 因州和紙 木版をタテヨコに滑らして作られたデザイン。色の重なりから見られる濃淡の奥行きや人の手の動きを感じます。手加工品だからこそ伝わる力強さです。


WWT30353

いのうえ・まさひろ
京都生まれ、京都在住。一級表装技能士。神社・仏閣の表装をはじめ、日本画・書に関わる軸装・額装・屏風等、表装の新調と修復を手掛ける。近年は、日本画家・書家の表装作品をはじめ、現代アートと京表具を融合させた作品の制作など、現代建築様式へのアプローチとして京表具で使用する伝統的な材料と技法を活かし、新しいアート・デザインを取り入れた表装作品も数多く制作している。
京表具 井上光雅堂
https://kogado.jp/
Instagram
https://www.instagram.com/kogado/